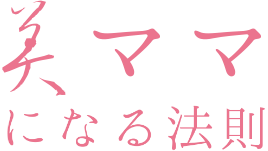好き嫌いはむしろ自然!
幼少期のうちから表れてくる子どもの好き嫌い。
両親も、将来大きく育ってほしいと好き嫌いを直すのに必死になりますが、頑固な子どもだと親子げんかになることも……。
好き嫌いを何とか直そうと必死になる前に、まずは両親のほうも、「子どもの好き嫌いは自然なことである」ということを理解しておく必要があります。
幼児期のうちは特に、酸味と苦味を嫌がる傾向があります。
このふたつは、実は生物にとって危険なサインであり、「酸味=腐っている」、「苦味=毒物」と結びついていることから、ほとんどの子どもが本能的に拒否すると言われています。
好き嫌いは、種としての生存本能でもあります。
もしも、すべての人間がトマトを好きだったらどうでしょう。
かぎられた資源の中ではトマトが少なくなり、最終的にすべての食物が消えてしまいます。
ある人はトマトが好き、ある人はキュウリが好き、またある人は……という風に、「好き嫌い」という要素を遺伝子レベルでくわえることで全体のバランスを取っているのです。
このように、好き嫌いを客観的にとらえることで、子どもの好き嫌いの理由も理解しやすくなります。
まずは理由を理解する
3歳以降から表れはじめる好き嫌いは、その子自身の個性や感性によるものです。
好き嫌いの理由としては、食感。味、食べ方、トラウマなどが考えられます。
このうち、食感や味、食べ方は調理法や組み合わせを工夫することで改善することができます。
一方、トラウマとはつまり、過去に嫌な記憶があるということですから、気持ちを理解せずに一方的に食べさせようとしてもトラウマを深めるばかりで、まったくの逆効果です。
いずれにせよ、まずは子供の立場になり、好き嫌いの理由を考えてみることが第一歩です。
無理やり食べさせようとしない
子どもの好き嫌いを直すうえで絶対にやってはいけないのが「無理やり食べさせる」ことです。
栄養があるから、おいしいからと大人が一方的に苦手なものを食べさせようとしても、子どもには嫌な想い出しか残らず、ますます嫌いになってしまいます。
気の弱い子どもは無理やり口に入れるかもしれませんが、それは気を遣っただけで、将来的に大人の顔色を見る性格に育ってしまう可能性も考えられます。
好き嫌いには、必ず理由があります。
大人の理屈だけを押しつけず、子どもが喜んで食べられる環境をつくってあげましょう。
家庭だけで解決しようとしない
子どもの好き嫌いは意外と複雑で、家庭では食べられなくても、学校で友達と一緒だったりすると食べられる、というケースも少なくありません。
そんな子どもに対して、「家でも食べなさいよ!」などときつく迫っては、せっかく芽生えかけた食への好奇心もなくなってしまいます。
好き嫌いは、子どもにとって初めての自己主張です。
両親としても好き嫌いは健全な成長だと受け止めつつ、食べることを楽しめるように心がけることがポイントです。